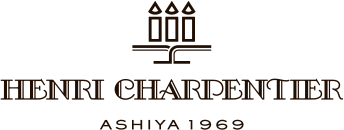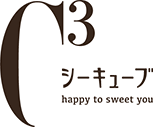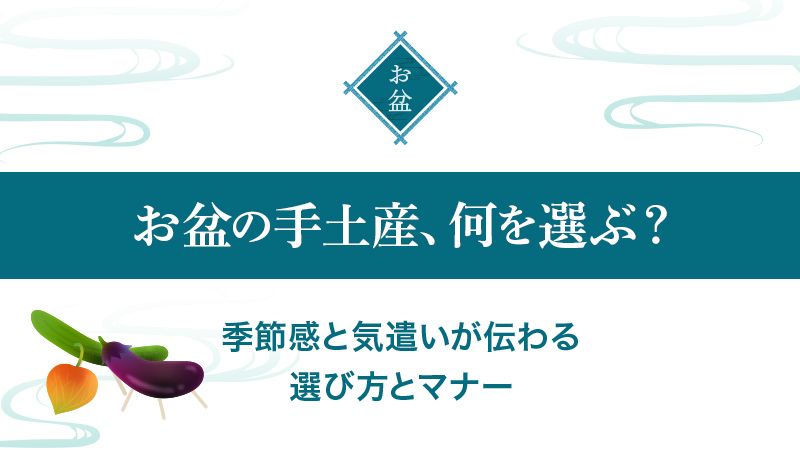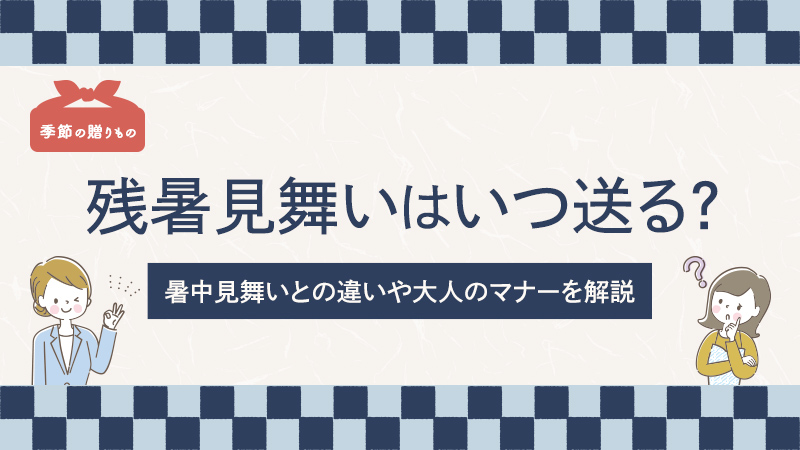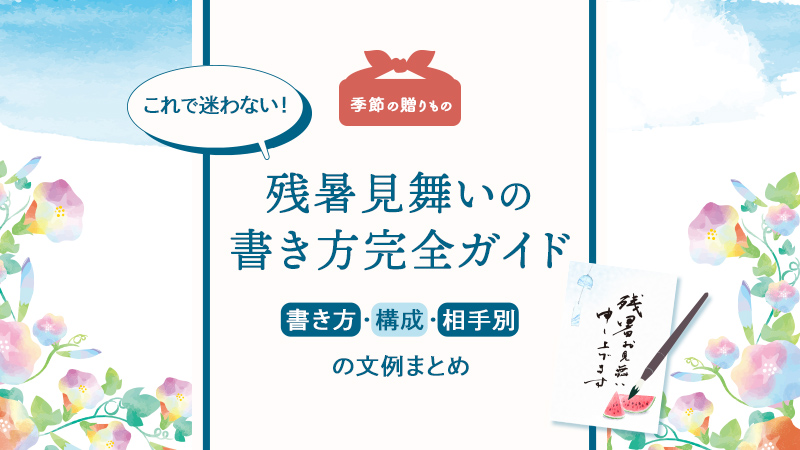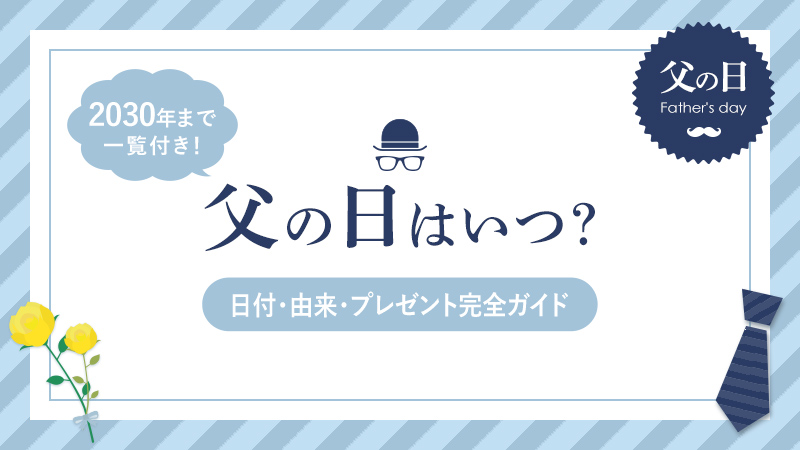長寿祝いは、人生の大切な節目を祝う重要な行事です。還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿といったお祝いには、それぞれの年齢にまつわる意味や伝統があり、その祝い方やプレゼントの選び方に悩む方も多いでしょう。
本記事では、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿の意味や祝い方、長寿お祝いにおすすめのギフトまで詳しく解説します。また、2024年版の長寿祝い早見表も用意しました。大切な方の長寿を祝う際に、ぜひ参考にしてください。
目次
還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿とは?
還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿といった長寿祝いは、日本の伝統的な文化の一部であり、人生の重要な節目を祝う行事です。
長寿祝いはお祝いの仕方に特に決まったものはなく、お祝いされる方の意向や家族の希望に沿った形でおこなうことが大切です。また、お祝いの日取りについても特に決まった規則はありません。家族が集まりやすい日程を選ぶのが一般的です。
還暦とは?60歳の祝い方と意味
還暦(かんれき)は、日本における伝統的な長寿祝いの一つで、61歳(満60歳)で祝われます。還暦の由来は、干支と十干の組み合わせが60年で一巡し、元の暦に戻ることからきています。
かつての日本では、現在よりも寿命が短く、60歳は長命で大変めでたいこととされていました。そのため、還暦は盛大に祝われ、家族や親戚が集まってお祝いするのが一般的でした。平均寿命が延びた今日では、60歳はまだ若く現役で活躍する方も多いことから、還暦は「感謝の気持ちを贈る節目」としてお祝いされるようになっています。
そして、還暦祝いでは、赤いちゃんちゃんこを着てお祝いする方が多いです。これは赤子に戻りもう一度生まれ変わって出直すという意味や、男性の場合は還暦と厄年が重なっているため、魔除けや厄除けの意味があります。
古希とは?70歳の祝い方と意味
古希(こき)は、70歳を迎えた際に祝われる長寿祝いです。古希の由来は、中国の唐代の詩人・杜甫の詩「人生七十古来稀なり」という一節にあります。この詩は「古来より70歳まで生きる人は稀である」という意味を持ち、長寿の象徴として古希が祝われるようになりました。
古希は数え年で70歳(満69歳)に祝うのが古くからの習わしでしたが、近年では満年齢で70歳を迎える年にお祝いすることが一般的になっています。どちらの年齢でお祝いしても問題はありません。古希のお祝いにおいては、紫色のアイテムを贈ることが定番です。
喜寿とは?77歳の祝い方と意味
喜寿(きじゅ)は、77歳を迎えた際に祝われる長寿祝いです。喜寿という言葉は、「喜」の字が草書体で「㐂」と書かれ、「七十七」に見えることに由来します。このため、喜寿は日本独自の長寿祝いの一つとして、室町時代末期から続く習わしとされています。
古くは数え年で77歳(満76歳)に祝うのが一般的でしたが、近年では満年齢で77歳を迎える年にお祝いすることが増えてきました。どちらの年齢で祝っても問題はありません。喜寿のお祝いに際しては、紫色のアイテムを贈ることが定番です。
傘寿とは?80歳の祝い方と意味
傘寿(さんじゅ)は、80歳を迎えた際に祝われる長寿祝いです。傘寿の由来は、「傘」という漢字の略字「仐」が「八十」と読めることからきています。このため、傘寿は80歳の節目におこなわれる長寿祝いとして定着しました。
傘寿も、古くは数え年で80歳(満79歳)に祝うのが一般的でしたが、現代では満年齢で80歳を迎える年にお祝いすることが一般的になっています。傘寿のお祝いに際しては、黄色や金茶色のアイテムを贈るのが定番です。
米寿とは?88歳の祝い方と意味
米寿(べいじゅ)は、88歳を迎えた際に祝われる長寿祝いです。米寿の由来は、「米」という漢字が「八十八」に見えることからきています。このため、88歳という節目に米寿のお祝いをおこなうのが習わしとなりました。
米寿も、古くは数え年で88歳(満87歳)に祝うのが一般的でしたが、現代では満年齢で88歳を迎える年にお祝いすることが主流となっています。米寿のお祝いでは、黄色や金茶色のアイテムを贈るのが定番です。
数え年と満年齢の違いは?
長寿祝いをおこなう際に、重要なポイントとなるのが「数え年」と「満年齢」の違いです。数え年とは、赤ちゃんが生まれた年を1歳とし、年が明けるごとに1歳ずつ加えていく方法です。このため、数え年では、誕生日を迎える前に年齢が増えることになります。一方、満年齢は、誕生日を基準に、その日を迎えるごとに1歳ずつ加えていく方法です。
現代では、日常生活においては満年齢を使用することが一般的ですが、伝統的な行事や祝い事では数え年が用いられることも多くあります。長寿祝いに関しては、もともとは数え年で祝うのが習わしでした。しかし、現在では満年齢で祝うことが増えており、特に厳密な決まりはありません。
還暦祝いだけは、伝統的に「数え年」で61歳、「満年齢」で60歳におこなうとされていますが、その他の長寿祝いにおいては、家族や本人の希望に応じて決めるとよいでしょう。
長寿祝い早見表|2024年(令和6年版)
| 読み方 | 祝う年齢 | 満年齢で祝う場合の生まれ年 | 数え年で祝う場合の生まれ年 | お祝いカラー | |
| 還暦 | かんれき | 60歳 | ー | 1964年(昭和39年) | 赤色 |
| 古希 | こき | 70歳 | 1954年(昭和29年) | 1955年(昭和30年) | 紫色 |
| 喜寿 | きじゅ | 77歳 | 1947年(昭和22年) | 1948年(昭和23年) | 紫色 |
| 傘寿 | さんじゅ | 80歳 | 1944年(昭和19年) | 1945年(昭和20年) | 黄色・金茶色 |
| 米寿 | べいじゅ | 88歳 | 1936年(昭和11年) | 1937年(昭和12年) | 黄色・金茶色 |
還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿のプレゼント の選び方
長寿祝いのプレゼントを喜んでもらうためには、選び方も大切なポイントです。
ここからは、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿のプレゼントの選び方について紹介します。長寿祝いで何を贈ろうか迷われている方は、ぜひ参考にしてください。
長寿祝いに贈るプレゼントは?
長寿祝いには、一般的には、旅行や食事会などを贈るのがおすすめです。家族や親戚で共に過ごす時間をプレゼントすれば、素敵な思い出を作ることができます。
また、還暦祝いでは、赤い頭巾やちゃんちゃんこを贈る風習があります。その他の長寿祝いでは、特に決まったプレゼントの風習はないので、それぞれのお祝いに関連する色を取り入れた品を贈るとよいでしょう。
また、プレゼントの品としては、お花、お酒、食器、高級食材、趣味に関連するアイテムなども人気があります。
長寿祝いのプレゼントの金額相場は?
長寿祝いは、贈る相手との関係性によって金額相場が異なります。たとえば、両親へのプレゼントの場合、2〜3万円程度が目安となります。
一方で、祖父母へのプレゼントの場合、1〜2万円程度が一般的です。また、親戚へのプレゼントについては、1万円前後が相場となります。
もし高価なプレゼントを贈りたいと考える場合には、家族や兄弟と共同で購入するのもよいでしょう。たとえば、旅行券や高級レストランのディナー券など、家族全員で贈ることで、より豪華で特別なプレゼントを用意できます。
長寿祝いのプレゼントを選ぶ際の注意点
長寿祝いのプレゼントでは、避けたほうがよいアイテムもいくつか存在します。
たとえば、老眼鏡や杖のような「老い」を感じさせるものは、せっかくのお祝いの席で不適切とされる場合があります。また、日本茶や刃物、ハンカチなども、縁起が良くないとされることがあるため、これらのプレゼントは避けるのが無難です。
さらに、花のプレゼントを考える際にも注意が必要です。たとえば、椿やシクラメン、菊の花などは、長寿祝いにはふさわしくないとされているため、避けることが望ましいです。
プレゼント を渡すタイミング
長寿祝いのプレゼントを渡すタイミングについては、特に厳密なルールはありません。
もし、長寿祝いの食事会やパーティーをする場合には、その場でプレゼントを渡すのが一般的です。一方で、食事会やパーティーが開かれない場合には、誕生日の1週間前から当日までの期間にプレゼントを渡すとよいでしょう。
まとめ|長寿の祝いにふさわしいプレゼント を贈りましょう
長寿祝いは、人生の節目となる大切なイベントです。還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿それぞれの祝い方や意味を知り、ふさわしいお祝いやプレゼントを贈りましょう。
プレゼントを選ぶ際には、相手の好みやライフスタイルを考慮し、喜んでもらえる品を選ぶことが大切です。長寿のお祝いは、家族の絆を強める貴重な機会。旅行や食事会、心のこもったプレゼントなどを贈れば、長寿祝いがより感動的で記憶に残るものとなるはずです。
アンリ・シャルパンティエではギフトシーンや季節やに合わせて、さまざまなギフト商品をご用意しています。ぜひご活用ください。