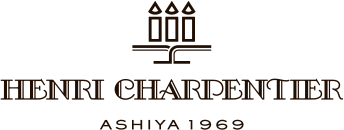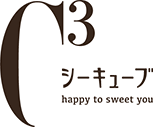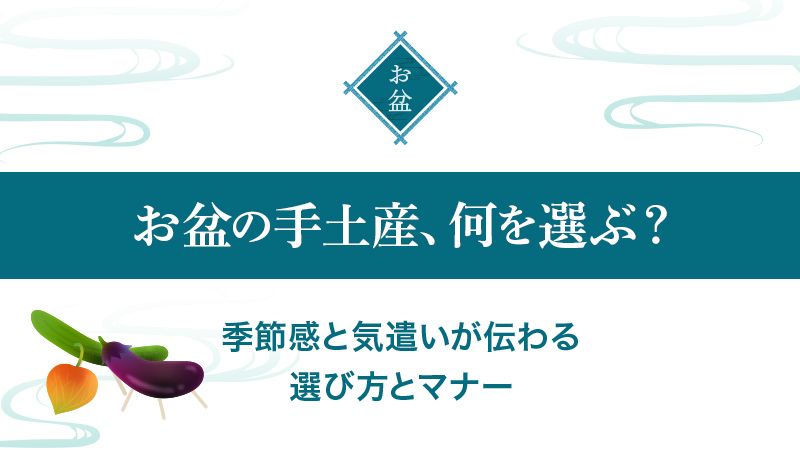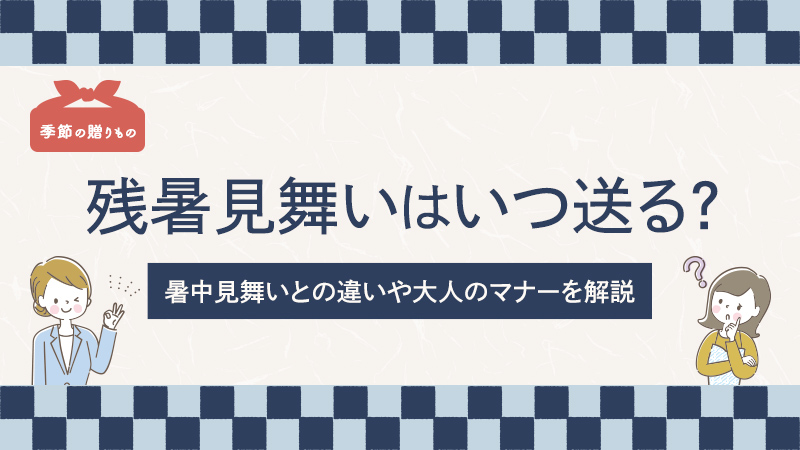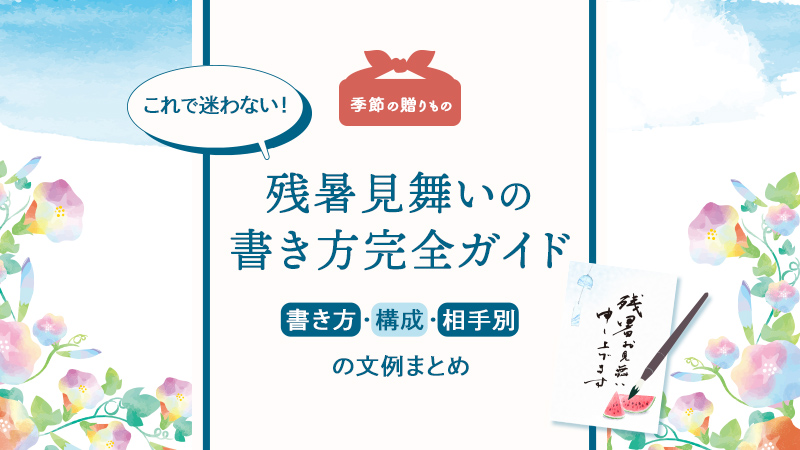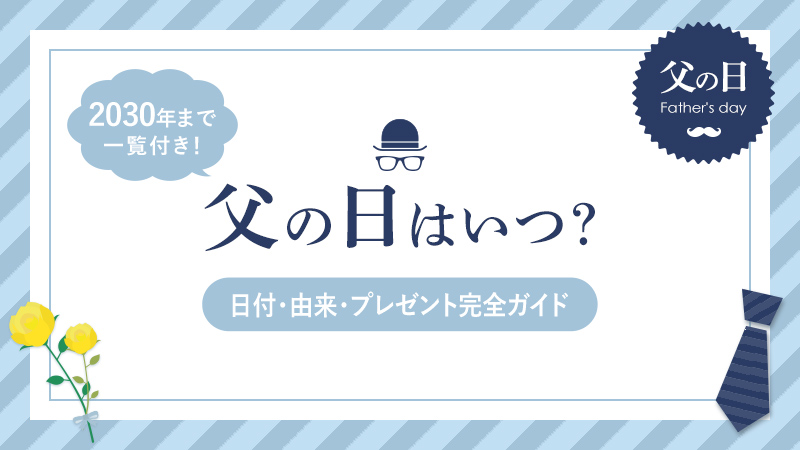クリスマスは世界中で祝われる行事のひとつですが、その歴史や背景について意外と知られていないかもしれません。
本記事では、クリスマスの歴史やサンタクロースの由来や、日本のクリスマス文化について紹介します。クリスマスの起源や歴史に興味がある方はぜひご覧ください。
目次
クリスマスの歴史
クリスマスは、もともとキリスト教における重要な祭日として誕生し、「イエス・キリストの降誕祭」として広く知られています。
キリストは今から約2000年前、ユダヤのベツレヘムにある馬小屋で聖母マリアから生まれたとされています。クリスマスを「イエス・キリストの誕生日」と認識されることもありますが、新約聖書にはキリストの具体的な誕生日の記載はありません。そのため、クリスマスはあくまで「キリストの生誕を祝う祭り」として位置づけられています。
なお、クリスマスがいつ始まったのか正確な時期は明らかになっていません。
まずは、クリスマスの起源と歴史的背景、また12月25日に祝われるようになった由来について詳しく紹介します。
クリスマスの起源と歴史的背景
クリスマスの起源には諸説ありますが、有力な説として2〜4世紀の古代ローマ帝国時代の祝祭に由来すると考えられています。クリスマスの歴史は非常に古く、キリスト教の広まりとともに、各地の伝統や祭りと融合しながら発展してきました。
クリスマスが12月25日に祝われる背景には、古代ローマの信仰が深く関わっています。もともと12月25日は、古代ローマで信仰されていた太陽神ミトラを称える「不敗の太陽の日」とされ、冬至を祝う重要な行事でした。また、ローマ帝国では農耕を祝う土着の祭りも12月25日前後におこなわれていたとされています。
ローマ皇帝はイエス・キリストを「光」にたとえ「光(太陽)の復活はキリストの復活」とし、「不敗の太陽の日」や土着の祭りを全て吸収する形で12月25日をキリストの降誕祭に制定しました。これは、ほかの宗教との対立を防ぐための折衷案としての意味合いもあったといわれています。
クリスマスイブとクリスマスの違い
クリスマスイブとクリスマスは、一般的に「クリスマス前日」と「クリスマス当日」として区別されていますが、実際にはどちらもクリスマスの大切な時間です。
また、クリスマスイブとクリスマスの違いには、キリスト教の前身であるユダヤ教の暦が関係しています。
「イブ」とは「夜」を意味する古語「even」に由来し、クリスマスイブは「クリスマスの夜」を指します。ユダヤ教の暦では1日の始まりを日没とするため、「12月24日の日没から12月25日の日没まで」が1日としてとらえられます。このため、12月24日の夜は「クリスマスの始まり」となり、深夜までクリスマスのお祝いが続きます。つまり、クリスマスイブは「クリスマス前夜」ではなく、すでに「クリスマスの夜」として含まれているのです。
現代では、教会や宗派によって解釈が異なりますが、一般的には日付が変わるとクリスマスと認識されることが多く、宗派や伝統に応じてさまざまな形でクリスマスイブとクリスマスが祝われています。
サンタクロースの由来
クリスマスの象徴的な存在であり、子どもたちにとって欠かせないサンタクロースは、4世紀頃、東ローマ帝国小アジアのシュラ(現在のトルコ)で活躍したキリスト教の司祭、聖ニコラウスに由来します。
聖ニコラウスは、貧しい人々や困っている人々を助ける心優しい人物として知られていました。彼の伝承には、貧しい家庭の娘たちのために金貨をそっと窓から投げ入れ、その金貨が偶然靴下に入ったという逸話があります。このエピソードが各地で語り継がれるうちに、聖ニコラウスはクリスマスの夜に贈りものを届けるサンタクロースとして神話化されました。「サンタクロース」という名前も、セント・ニコラウスの名が訛ったものです。
さらに、19世紀にアメリカのイラストレーターがサンタクロースを赤い服と白いひげの姿で描いたことがきっかけで、現代のサンタクロース像が定着し、子どもたちに夢や希望を届ける象徴として世界中で親しまれるようになりました。
クリスマスカラーや飾りの意味を知ろう
クリスマスシーズンになると、街は赤と緑の華やかな飾りで彩られ、クリスマスツリーやリースが私たちの目を楽しませてくれます。しかし、これらの色や飾りには深い意味が込められていることをご存じでしょうか。
ここでは、クリスマスをより楽しむために、クリスマスカラーやツリーに込められた意味、ケーキやアドベントカレンダーの習慣について詳しく紹介します。
クリスマスカラーはなぜ赤と緑なのか
クリスマスの象徴的なカラーである「赤」と「緑」には、深い意味が込められています。
赤は「キリストの血」を象徴し、「愛や寛大さ」を表す色です。一方、緑はクリスマスに飾られるモミの木やヒイラギなどの常緑樹を象徴し、冬の厳しい寒さのなかでも枯れることのない「永遠の命」や「希望」を意味します。
赤や緑の色は、クリスマスツリーやリース、オーナメントなどに多く使われ、華やかで温かみのある雰囲気を演出しています。
ツリーに込められた願いと意味
クリスマスツリーに使われるモミの木などの常緑樹は、冬の寒さのなかでも枯れないことから「永遠の命」を象徴しています。
ツリーを飾るようになった背景には、古代ゲルマン民族の信仰が関係しています。言い伝えによると、古代ゲルマン民族は寒さに強い樫の木を永遠の象徴として崇拝していましたが、キリスト教の宣教師が彼らを改宗させるために樫の木を切り倒したところ、そのそばからモミの木が芽生えたといわれています。この出来事がきっかけで、モミの木がクリスマスツリーとして用いられるようになったとされているのです。
また、ツリーの飾りにもそれぞれ意味が込められています。頂点に飾られる星型のオーナメントはイエス・キリストの誕生を知らせた「ベツレヘムの星」、丸いボールはアダムとイブが食べた「禁断の果実」を表しています。
クリスマスケーキを食べる理由は?
クリスマスにケーキを食べる習慣は、もともとイエス・キリストの誕生を祝うバースデーケーキが由来だとされています。
日本ではいちごのショートケーキがクリスマスケーキとして親しまれていますが、クリスマスに食べるケーキは国によって異なります。
たとえば、フランスでは「ブッシュ・ド・ノエル」、イタリアでは「パネトーネ」、イギリスでは「クリスマスプディング」、ドイツでは「シュトーレン」などが定番です。
クリスマスケーキは多くの家庭で楽しむイベントのひとつとなっていますが、人気のケーキは早々に売り切れるため、事前に予約しておくことが大切です。クリスマスケーキの予約に関しては、以下の記事をご参照ください。
関連記事:クリスマスケーキの予約はいつから始まる?予約購入のメリットも解説
アドベントカレンダーの楽しみ方
アドベントカレンダーは、クリスマスを待ち望む期間である12月1日から24日までの日々を楽しくカウントダウンするためのカレンダーです。一般的には、カレンダーに小窓や扉があり、毎日1つずつ開けると中にお菓子や小さな贈りもの、メッセージが入っています。
もともとはキリスト教の伝統行事として、クリスマスを待つ時間を大切にするためのものとして始まりましたが、現在では宗教的な意味合いに限らず、親子で楽しむイベントや友人同士で贈り合うギフトとして広まっています。市販のアドベントカレンダーも人気ですが、家族や友人と手作りしてみるのもおすすめです。
アドベントカレンダーを使うことで、お子さまや大切な人と毎日小さな窓を開ける喜びを分かち合いながら、クリスマス当日までの期待感を高めることができるでしょう。
日本での最初のクリスマスはどんなものだった?
日本にクリスマスが伝わったのは16世紀の戦国時代のことで、キリスト教の宣教師たちによってもたらされました。フランシスコ・ザビエルとともに日本で布教したコスメ・デ・トレースが、1552年に現在の山口県において降誕祭をおこなったのが日本での最初のクリスマスといわれています。
しかし、当時はキリスト教徒が限られていたため、クリスマスも一部の地域で限定的に祝われていました。そのあと、江戸時代のキリシタン弾圧によりキリスト教の行事が抑制され、一時的にクリスマスの風習は姿を消しています。
明治時代の文明開化によって再びクリスマスが紹介されると、都市部を中心に広まり始めました。そして戦後には、クリスマスが商業イベントとして浸透し、日本ならではの文化が形成されるようになったのです。デパートや商店街でのクリスマス商戦が展開されるようになると、プレゼントやケーキを用意する家庭が増え、クリスマスは日本の一般的なイベントとして根付いていきました。
戦後に定着した日本ならではのクリスマス
戦後の高度経済成長期、デパートのクリスマス商戦が活発化したことで、クリスマスが日本の文化に定着していきました。
日本独特のクリスマスケーキ文化が広がったのは1950年代で、洋菓子メーカーが「クリスマスにはケーキを」というキャッチコピーで宣伝をおこなったことがきっかけです。ホイップクリームと苺で飾られたケーキは、クリスマスの象徴として欠かせない存在となりました。
また、昭和後期から平成初期にかけては、クリスマスは恋人同士が過ごす日というイメージが強まっていきました。イルミネーションや華やかな飾りつけが都市部で盛んにおこなわれ、12月24日には恋人同士がレストランでディナーを楽しむといったスタイルが一般化しています。
さらに、クリスマスイブやクリスマス当日には、家族や恋人とのプレゼント交換が定番となり、一年の感謝や愛情を表現する機会として広まりました。
こうして発展した日本特有のクリスマス文化は、欧米とは異なる独自のスタイルとして現在も多くの人に親しまれています。
海外のクリスマスについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:海外と日本のクリスマスの過ごし方を比較|おすすめの過ごし方も紹介!
まとめ|クリスマスの歴史と文化を知って、より深く楽しもう
クリスマスは、もともと宗教的な意味合いをもつ行事として始まりましたが、長い歴史のなかでさまざまな文化や国の影響を受け、現在では世界中で祝われる一大イベントへと発展しました。
特に日本では、商業的な影響を受けながらも独自の風習が生まれ、家族や恋人同士で過ごす特別なイベントとして親しまれています。クリスマスケーキやイルミネーションなど、それぞれの楽しみ方が多くの人々に広がり、今では日本の年末に欠かせない行事となっています。
また、クリスマスを彩るスイーツとして、日本のクリスマスケーキ文化も見逃せません。
アンリ・シャルパンティエでは、クリスマスにぴったりの華やかなケーキをご用意しています。今年のクリスマスケーキにぜひご検討ください。