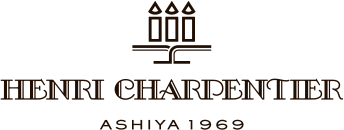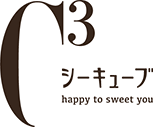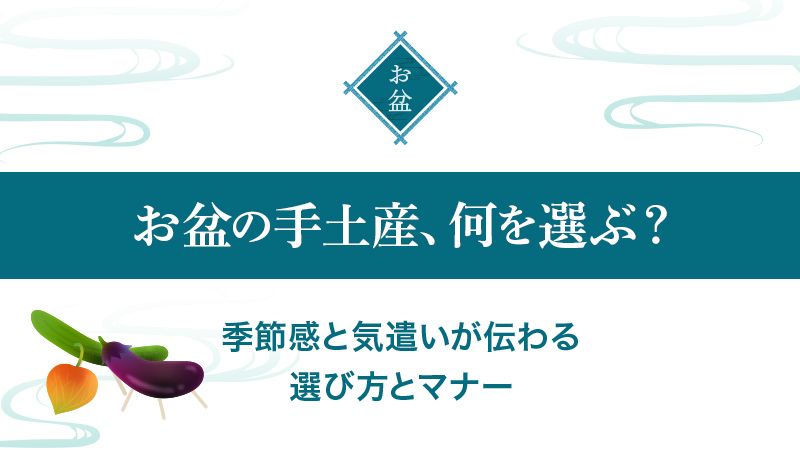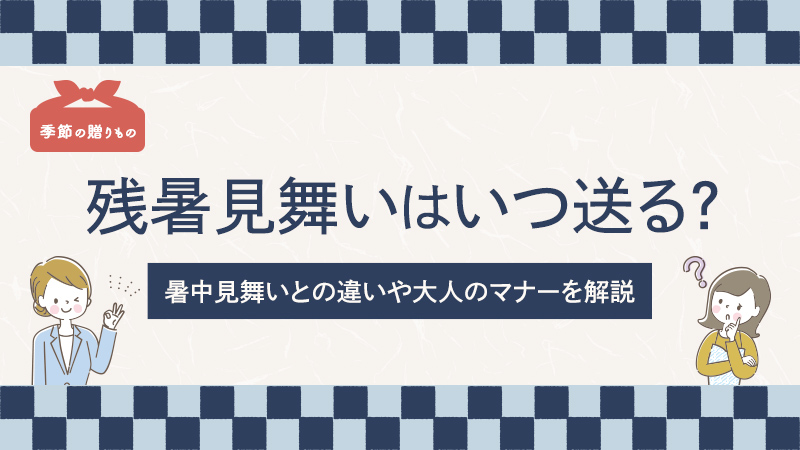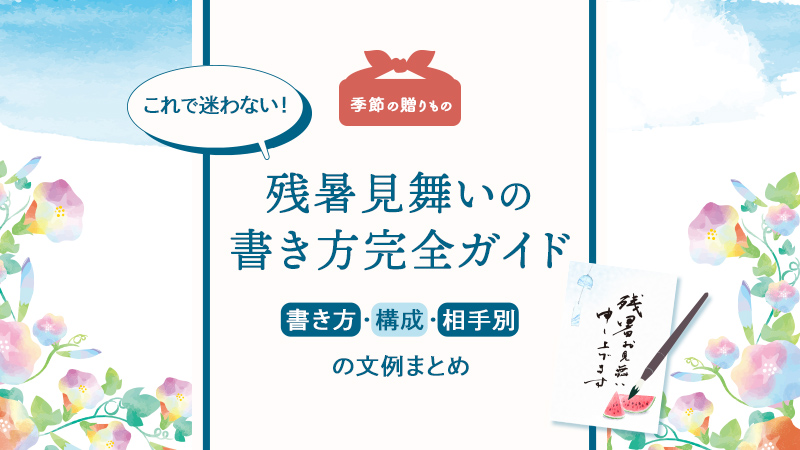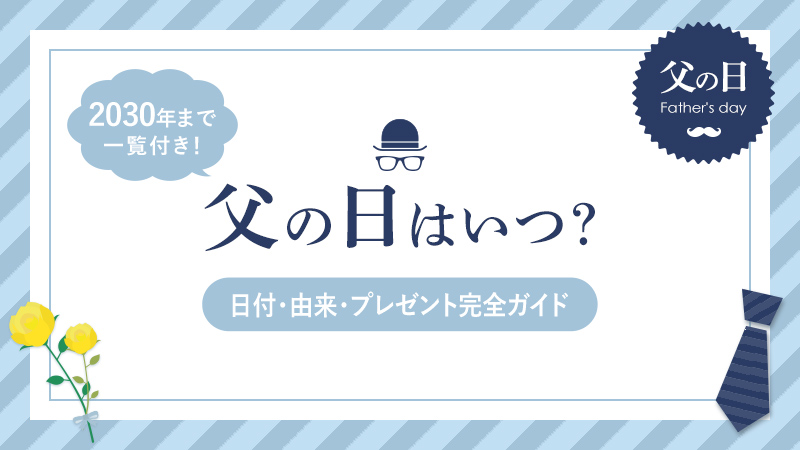初盆(はつぼん)とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を指します。通常のお盆と比べて、より丁寧に供養するのが特徴です。
初めてのお盆を迎えるにあたり、「何を準備すればよいのか」「どのように進めるべきか」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、初盆の基本的な意味や時期、準備すべきこと、当日の流れ、注意点までを順を追って解説します。大切な故人を偲ぶための参考にしてください。
目次
初盆とは|故人を偲ぶ初めてのお盆
初盆(はつぼん)は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を指します。家族や親族にとって、故人の魂を迎え入れ、供養する大切な行事です。
ここでは、初盆の基本的な意味や由来、通常のお盆との違いについて解説します。
- 初盆(新盆)の意味と由来
- 一般的なお盆との違い
初盆(新盆)の意味と由来
初盆(はつぼん)または新盆(にいぼん)とは、故人が亡くなって四十九日の忌明けを過ぎてから迎える、最初のお盆 のことです。
日本では毎年8月(地域によっては7月)にご先祖様の霊を迎えて供養する「お盆」の行事がおこなわれますが、初盆はそのなかでも特に重要な節目とされています。
人は亡くなると、あの世への旅路を経て四十九日で成仏する とされています。初盆は成仏した魂が初めて自宅に戻ってくる一度きりの機会であるため、特別な意味を持つ のです。
また、初盆は故人の冥福を祈るとともに、遺された家族が悲しみを分かち合い、絆を確かめ合う大切な機会でもあります。
一般的なお盆との違い
初盆は、一般的なお盆と比べて、より丁寧な供養がおこなわれるのが特徴です。
通常のお盆は、先祖の霊を迎えて供養する年中行事ですが、初盆は故人が亡くなってから初めて自宅に戻ってくる特別な機会 とされています。そのため、白い提灯を飾ったり、僧侶を招いて法要を営んだり と、手厚く供養するのが一般的です。
また、親族や故人と縁の深い方々を招いて会食を開く ことも多く、感謝と追悼の気持ちを共有する場となります。こうした丁寧な準備や対応が、一般的なお盆と初盆の違いといえるでしょう。
初盆はいつおこなう?
初盆は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆の時期におこないます。通常は毎年8月13日から16日までが一般的ですが、地域によっては7月におこなうところもあります。
大切なのは、四十九日の法要を終えてから初めて迎えるお盆であることです。四十九日前にお盆を迎える場合、その年は初盆とされません。
初盆にあたるかどうかを判断するには、まず故人の命日と四十九日の時期を確認しましょう。日程が確定したら、法要の準備や僧侶への依頼を早めに進めます。
初盆の準備|事前にしておくこと
初盆を迎えるにあたり、僧侶への依頼や飾り物、お供え物の用意などをする必要があります。
その内容は地域の風習や家族の考え方によって異なりますが、以下に、主な準備項目を紹介します。
- 僧侶に読経を依頼する
- 白提灯を用意して飾る
- 盆棚(精霊棚)を準備する
- 花や果物、お菓子などのお供え物を用意する
- 参列者への案内と会食(お斎)の準備をする
- お返し(引き物)を用意する
以下で詳しく見ていきましょう。
僧侶に読経を依頼する
初盆では、僧侶に読経をお願いして故人の供養をおこないます。読経は初盆の中心的な行事になります。
読経を依頼する際は、菩提寺がある場合はその僧侶へ、ない場合は葬儀を依頼した業者などに相談するとよいでしょう。場所は、自宅や菩提寺、葬儀会館などでおこないます。
夏の時期は僧侶の予定も混み合うため、早めの問い合わせがおすすめです。
白提灯を用意して飾る
初盆では、玄関先に「白提灯」を飾る のが一般的です。白提灯は、通常のお盆とは異なる初盆特有の風習です。故人の霊が迷わずに帰ってくるための目印の役割 を持ちます。
ただし、地域や宗派によっても異なる ため、親族に習わしを確認しておくとよいでしょう。
白提灯は初盆用であり、使い回すことがないため、使用後はお寺でお焚き上げをしてもらいます。
盆棚(精霊棚)を準備する
盆棚や精霊棚(しょうりょうだな)は、故人の霊を迎え入れるために用意する祭壇です。仏壇の前や別のスペースに設け、位牌やお供え物、故人の写真などを飾ります。
家庭用の簡易な盆棚セットも市販されており、スペースや予算に応じて用意ができます。地域の習慣によって棚の飾り方や使用する道具が異なるため、親族やお寺に確認して準備を進めましょう。
盆棚の用意をすることで、故人を迎える準備が整います。
花や果物、お菓子などのお供え物を用意する
初盆では、故人が喜ぶものを供えることで、感謝と敬意を表します。一般的に選ばれるのは、季節の花や果物、お菓子や故人の好物などです。
花は白を基調とした落ち着いた色合い が好まれますが、地域や宗派によって異なる場合もあります。お供え物は、常温保存可能な日持ちするものが適しています。
故人との思い出を大切にしながら、お供え物を選ぶとよいでしょう。
関連記事:お盆のお供えにお菓子がおすすめな理由は?選び方やマナー、相場を解説
参列者への案内と会食(お斎)の準備をする
初盆では、故人と縁のあった親族や知人を招いて供養をおこないます。
最近では家族や親族のみで過ごすケースも増えていますが、知人やお世話になった方に参列をお願いする場合は、案内状や口頭で参加の可否を確認します。
会食(お斎)を準備する場合は、人数やアレルギーなどに配慮してメニューを決めましょう。自宅でおこなう場合と会場を借りる場合では準備方法が異なるため、早めの計画が必要です。
お返し(引き物)を用意する
初盆に参列してくださった方々には、お返し(引き物)を用意するのがマナーです。お返しの品には、故人への供養に対する感謝の気持ちが込められています。
相手に負担をかけないよう、使う(食べる)となくなる洗剤やお茶、菓子折りなどの消耗品を選ぶとよいでしょう。地域によって風習が異なる場合もあるため、親族や葬儀社に相談しながら選ぶと安心です。
お返しの品物は、いただいた香典の半額から3分の1程度を目安 に用意し、掛け紙には「志」や「初盆志」などの表書きを添える のが一般的です。
初盆当日の流れ|迎え火・法要・送り火
初盆では、迎え火や法要、送り火などの行事を通じて故人の霊を迎え入れ、供養し、再び見送ります。主な流れは以下のとおりです。
- 迎え火を焚いて故人を迎える
- 僧侶による法要
- お墓参り
- 参列者と会食
- 送り火を焚いて故人を見送る
それぞれの流れを具体的に見ていきましょう。
迎え火を焚いて故人を迎える
迎え火は、お盆の入りである13日の夕方におこなうのが一般的です。故人の霊が迷わず帰って来るための、道しるべの意味を持ちます。
玄関先や墓前で、おがら(麻の茎)を用いて火を焚くのが伝統的な方法です。地域によっては火を使わず、提灯を灯して代用することもあります。
迎え火は、お盆のはじまりを告げる儀式であり、故人を迎える意味を持ちます。
僧侶による法要
僧侶を招いて読経をおこない、故人の冥福を祈る法要をおこないます。中日である14日か15日におこなわれるのが一般的 ですが、参列者の都合やお寺の予定にあわせて調整が必要です。
法要は自宅や菩提寺、葬儀会館などで開催されることが多く、祭壇にお供え物を並べ、焼香をして供養します。
読経の時間や流れは宗派によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
お墓参り
お盆期間中には、お墓参りをおこない、墓前でも故人を供養します。日程に決まりはありませんが、「早くお迎えする」という意味合いから、13日の午前中にお参りするのが適切とされる場合も あります。
墓前には、花や線香、食べ物や飲み物などを供えます。鳥や動物に荒らされてお墓が汚れるのを防ぐために、お参りが終わったら飲食物は持ち帰るのがマナーです。
なお、お盆の前にはお墓掃除も忘れずにおこない、きれいな状態で故人をお迎えしましょう。
参列者と会食
初盆の法要後には、参列者を招いて会食(お斎)をおこなうことがあります。これには、供養を終えたあとに故人を偲びながら、親族や知人と共に時間を過ごす目的があります。
仕出し弁当を用意したり、外部の会場を利用したりと、会食の形式はさまざまです。最近では家族のみで小規模におこなうケースも増えています。
参加人数や予算に応じて準備しましょう。
送り火を焚いて故人を見送る
送り火は、故人の霊をあの世へ見送るための儀式です。お盆の最終日である16日 におこなわれます。迎え火と同様に玄関先で火を焚く、または提灯を灯して見送るのが一般的です。
地域によっては川に灯籠を流す「灯籠流し」 や、大文字の送り火などの行事も見られます。送り火は、感謝の気持ちとともに故人の魂が安らかに帰ることを願う時間です。
温かい気持ちで見送りましょう。
初盆にまつわるマナーと注意点
初盆は、故人が亡くなってから初めて迎える特別な機会であるため、準備や当日の進行に加えて、マナーへの配慮も大切です。また、使用したお盆用品についても、適切に処分・保管する必要があります。
ここでは、初盆を迎える際に知っておきたいポイントをまとめて紹介します。
- 初盆にやってはいけないこと
- お盆用品の処分(ご供養)や保管方法
初盆にやってはいけないこと
初盆では、故人の魂を敬う気持ちを大切にするため、いくつかの配慮すべき点があります。
特に避けたいのは、華やかな演出や派手な服装、過度の飲酒などです。供養の場にふさわしくない振る舞いは、参列者にも不快感を与えるおそれがあります。
また、宗派や地域によっても作法があるため 、菩提寺に確認しておくと安心です。故人の冥福を第一に考え、静かで心のこもった供養をおこないましょう。
お盆用品の処分(ご供養)や保管方法
初盆で使用した白提灯やお供え物、飾りなどは、行事が終わったあと適切に処分または保管する必要があります。
白提灯はお寺でお焚き上げしてもらうか、送り火で燃やすのが一般的です。自宅で処分する場合は、塩をふって清めてから白紙で包み、可燃ごみに出す方法もあります。
次年以降も使うものは、ほこりや汚れを落としてきれいにしたあと、湿気を避けて丁寧に保管しましょう。
まとめ|初盆は故人を偲び、家族の想いをつなぐ行事
初盆は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆であり、故人を偲ぶとともに、家族や親族の絆を改めて感じる機会です。
通常のお盆以上に丁寧な供養がおこなわれることが多く、事前の準備や当日の進行、マナーに至るまで、さまざまな配慮が求められます。こうした一つひとつの心づかいが、故人への敬意を表すことにつながります。
初盆を通じて故人への感謝の気持ちや思い出を分かち合うことで、家族としてのつながりをあらためて実感できるでしょう。本記事を参考に初盆の準備を整え、心穏やかにその日をお迎えください。