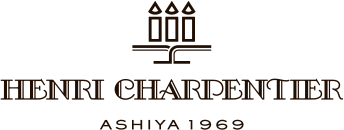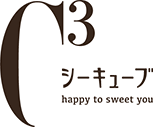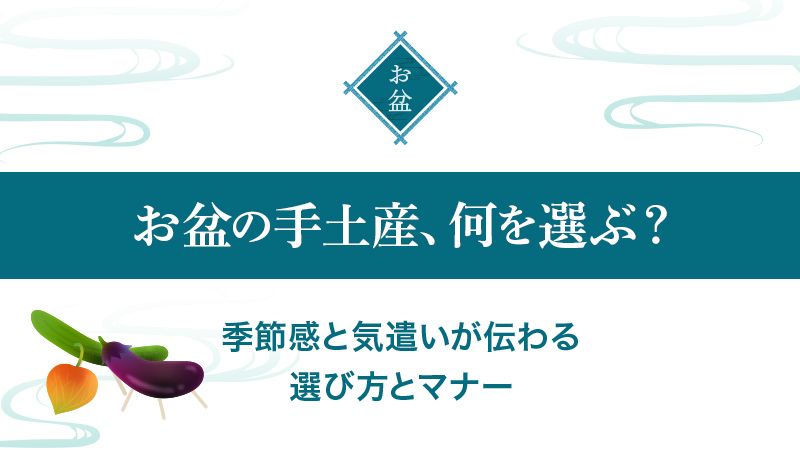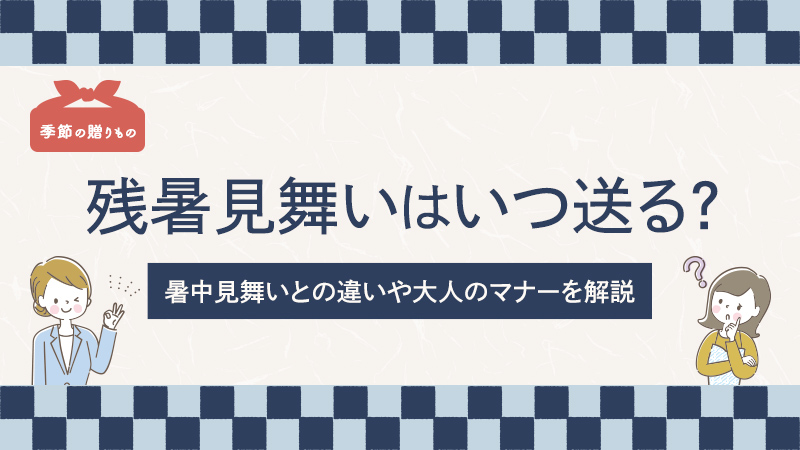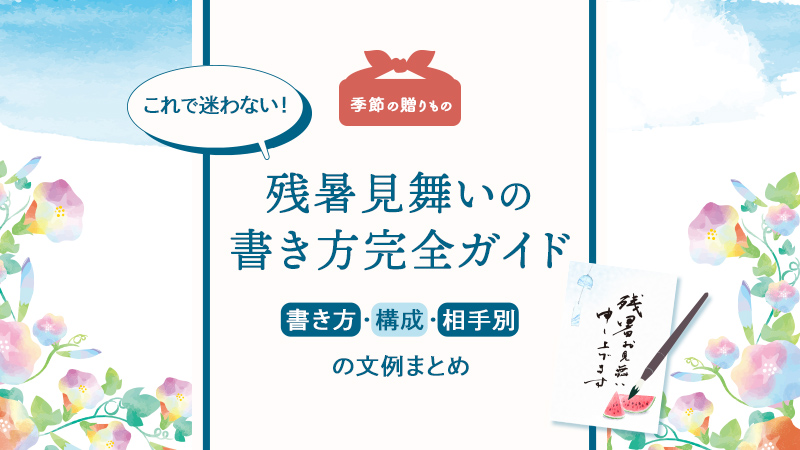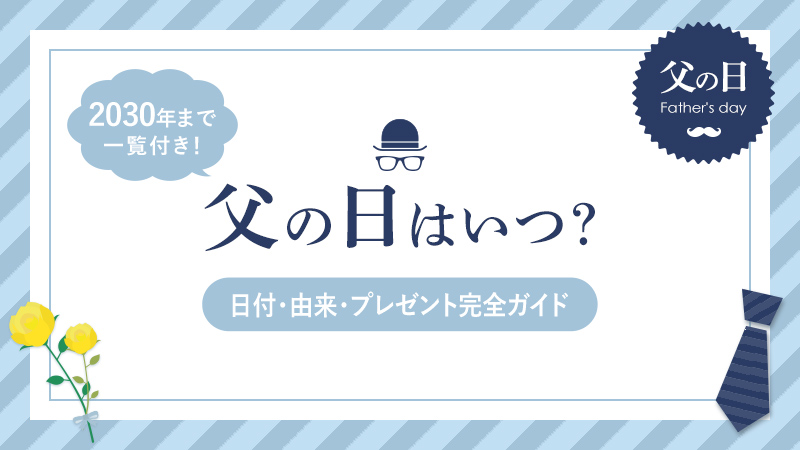結婚祝いをいただいた際は、感謝の気持ちを込めてお返しをするのがマナーです。しかし、お返しの準備には「贈る時期」「のしの書き方」「包装のルール」など、押さえておくべきポイントが多く、迷う方もいるのではないでしょうか。
本記事では、結婚祝いのお返しに関するマナーをわかりやすく解説します。適切な対応をすることで、相手に失礼なく、気持ちよく受け取ってもらうことができます。これからお返しの準備を進める方は、ぜひ参考にしてください。
目次
結婚祝いをもらってから準備までのスケジュールとポイント
結婚祝いを受け取ったら、スムーズにお返しができるよう準備を進めることが大切です。
ここでは、お礼を伝えるタイミングや品物の選び方など、具体的なスケジュールとポイントを解説します。
お祝いをいただいたら、すぐにお礼を伝える
結婚祝いをいただいたら、できるだけ早く電話でお礼の連絡をしましょう。早めに伝えることで、感謝の気持ちがしっかりと届き、相手にも喜んでもらえます。
メールや手紙で伝える方法もありますが、電話のほうが気持ちが伝わりやすく、より丁寧な印象を与えます。
また、電話をかける際は、忙しい時間帯を避けるなど、相手への配慮を忘れないようにしましょう。
お返しリストを作る
誰からどのようなお祝いをいただいたのかを整理し、お返しリストを作成しておくと安心です。
リストを作成するときには、いつ・誰から・どんなお祝いをいただいたのかをメモしておきましょう。金額や品物の内容に加え、住所や結婚式への招待有無などの情報もまとめておくと、スムーズにお返しの準備ができます。
また、お返しの品を相手ごとに変える場合は、種類ごとにリストを作成すると、準備の抜け漏れを防げます。
品物を選ぶ
リストが完成次第、早めに選び始めるとスムーズに準備できます。お返しの品物は、お相手の好みや金額を考慮しながら選ぶため、どうしても時間がかかってしまいます。スケジュールに余裕を持つと安心です。
また、結婚祝いのお返しを選ぶ際は、地域の慣習に配慮することも大切です。たとえば、いただいた結婚祝いの1割相当を挙式後の帰宅時にお渡しする「おため返し」をする地域もあるなど、地域ごとに慣習は異なります。事前に確認し、適切な品物を選ぶことで、より喜んでもらえるお返しになるでしょう。
お返しの品物の価格帯やおすすめのギフトについては、以下の記事もぜひ参考にしてください。
関連記事:結婚祝いのお返しと内祝いは違うもの?相場や喜ばれるギフトも紹介
お礼状を用意する
品物を選んだら、お礼状も準備しましょう。結婚祝いのお返しには、感謝の気持ちを伝えるお礼状を添えるのが一般的です。
ただし、直接手渡しする場合は口頭でお礼を伝えられるため、お礼状は不要です。代わりに、一言メッセージを添えるとよいでしょう。親しい友人には、お礼状の代わりにカジュアルなメッセージカードを利用しても問題ありません。
お礼状は手書きでも印刷でもマナー違反にはなりませんが、目上の方には縦書きの形式がよりフォーマルな印象を与えます。メッセージの内容は、相手との関係性に応じて使い分けるとよいでしょう。
お礼状に盛り込む内容例
- 時候の挨拶(フォーマルな形式では入れるのが望ましい)
- 時候の挨拶(フォーマルな形式では入れるのが望ましい)
- お礼の品を贈ったこと
- 新生活の近況報告やこれからの抱負
- 今後のお付き合いやご指導のお願いなど
お祝いのメッセージでは、忌み言葉や重ね言葉は避け、句読点を使わないのがマナーです。なお、お礼状では「お返し」という表現は避け、「お礼の品」と表現します。
結婚祝いのお返し|のし・包装のマナー
結婚祝いのお返しを贈る際は、品物だけでなく、のしや包装のマナーにも気を配ることが大切です。
ここでは、のしの種類や書き方、包装の選び方について詳しく解説します。
「のし」の選び方と書き方
結婚祝いのお返しには、「のし」紙を付けるのがマナーです。のし紙は、紅白の10本の水引で「結び切り」または「あわじ結び」を選ぶのが一般的です。
また、のしには「内のし」と「外のし」があり、贈る場面によって適したものを選びましょう。
| 内のし | 品物にのし紙を掛け、その上から包装紙を掛ける方法。配送で贈る場合に適しています。 |
|---|---|
| 外のし | のし紙を包装紙の外側に掛ける方法。贈りものであることを明確に伝えるため、手渡しの場合に適しています。 |
「のし」の表書きには、一般的に「内祝」と記載します。「寿」と書く場合もありますが、披露宴に招待しない方からのお祝いに対するお返しには「内祝」、結婚式の引出物には「寿」とすることが多いです。
贈る相手が喪中の場合には、「祝」という文字は避けて、表書きは「御礼」として贈るとよいでしょう。
また、名前の書き方にも注意が必要です。結婚祝いのお返しでは、以下のいずれかの形式で名前を記載します。
- 結婚後の新姓のみ
- ふたりの名前のみを連名で(右から順に夫の名前、妻の名前)
- 新姓の下にふたりの名前を連名で(右から夫の氏名、夫の名前の横に妻の名前)
- 両家連名で記載(右から順に夫の姓、妻の旧姓)
どの形式にするかは夫婦で相談して決めますが、親族へのお返しの場合は、親にも相談すると安心です。表書きや名前を書く際は、毛筆や筆ペンを使用しましょう。
包装や紙袋の選び方
結婚祝いのお返しを贈る際は、包装や紙袋にも気を配ることが大切です。包装紙の色やデザインは、華やかで上品なものを選びましょう。結婚祝いのお返しには、ピンクや花柄など、明るく柔らかい雰囲気のデザインがおすすめです。
また、手渡しする場合は、品物に汚れがつかないよう紙袋に入れるか、風呂敷に包んで持参するのがマナーです。紙袋を選ぶ際は、お返しの品を取り出しやすいよう、指を入れるスペースのあるサイズを選ぶとスマートに渡せます。デザインも、お返しにふさわしい落ち着いたものを選ぶとよいでしょう。
結婚祝いのお返しを渡す・送るタイミングと方法
結婚祝いのお返しは、贈るタイミングや方法にも注意が必要です。また、手渡しする場合と配送する場合でマナーが異なるため、それぞれのポイントを押さえておきましょう。
ここでは、結婚祝いのお返しを贈る適切な時期や渡し方について詳しく解説します。
お返しを贈る時期
結婚祝いのお返しは、結婚式後1ヵ月以内に贈るのがマナーとされています。結婚式をおこなわない場合は、入籍後1ヵ月以内を目安に準備しましょう。
挙式や入籍前にお祝いをいただき、お返しまで期間が空いてしまう場合は、挙式後や入籍後に改めてお礼することを事前に伝えておけば問題ありません。もしくは、受け取った日から1ヵ月以内に贈るのが望ましいです。
結婚式の日程が未定の段階でお祝いをいただいた場合も、受け取った日から1ヵ月以内を目安にお返しをするとよいでしょう。ただし、あまりに早すぎるお返しは失礼に感じられる可能性があるため、お祝いを受けてから2週間程度経過後に贈るのが適切です。
直接手渡しをする際のマナー
結婚式のお返しは、直接渡すことで感謝の気持ちをより伝えやすくなります。
手渡しをする際には、品物を紙袋に入れて持参し、渡す際には袋から出して両手で相手に渡すのが基本です。紙袋や風呂敷は持ち帰りましょう。
また、「ささやかですが、感謝の気持ちです。どうぞお受け取りください」といった一言を添えると、より丁寧な印象になります。相手の都合を考慮し、事前に訪問のアポイントメントを取ることも忘れないようにしましょう。
配送する際のマナー
遠方に住んでいる方や、多忙でなかなか会うのが難しい方には、配送でお返しを贈っても問題ありません。
配送する際は、相手が受け取りやすい日時を事前に確認し、都合のよいタイミングで送ると丁寧です。また、感謝の気持ちを伝えるお礼状やメッセージカードを贈ることも大切なマナーです。
お礼状は、本来であれば品物が相手に届く前に送るのが正式なマナーですが、品物に同封しても問題ありません。
まとめ|結婚祝いのお返しは、事前準備とマナーが大切
結婚祝いのお返しは、感謝の気持ちを形にして伝える大切な機会です。お祝いをいただいたら、まずは迅速にお礼を伝え、その後リストを作成して計画的に準備を進めましょう。適切なタイミングやマナーを意識することで、より心のこもったお返しができます。
アンリ・シャルパンティエでは、結婚祝いのお返しにふさわしい、上品な味わいと華やかなデザインの焼き菓子ギフトを豊富に取り揃えています。ぜひご検討ください。
>>ギフトを選ぶ|アンリ・シャルパンティエ公式通販